安全で適正な富士登山のために情報を集約
富士登山オフィシャルサイト
1 富士登山オフィシャルサイトの概要
富士登山オフィシャルサイトは、環境省・山梨県・静岡県が協力して運営する「富士登山のための総合サイト」で、登山者に必要な公式情報を幅広く提供することを目的としています。
サイトには緊急情報を筆頭に、「登山の前に必ず知っておくこと」「登山をより楽しむために」「今日の富士山」など、目的別に整理された主要カテゴリが並び、伝わりやすさを重視した、視覚的にも落ち着いた構成です。
2 サイトのターゲット
富士登山オフィシャルサイトの主なターゲットは、これから富士登山を計画している初心者から中上級者の登山者です。
公式サイトらしく、安全な登山の方法や計画の基本から、登山ルートの比較、装備やマナー、マイカー規制や混雑カレンダーまで、幅広い情報を網羅しています。初心者には「弾丸登山のリスク」や「高山病対策」「ゆとりある行程のすすめ」といったアドバイスが、丁寧な語り口で紹介されています。
3 トップページの印象
富士登山オフィシャルサイトのトップページファーストビューは、緑の木々に包まれた森の奥に、堂々たる富士山を望む背景画像が表示されます。
富士山に関連するサイトに相応しいビジュアルですが、目立つのはこの画像ではありません。
ビジュアル上には、アイコンナビゲーションと共に、【緊急情報】、【重要情報】、【警報・注意報】、【噴火警戒レベル/予報警報】といった情報が非常に目を惹くかたちで表示されています。
このサイトの目的『安全な富士登山を推進』する為に一番重要な情報が、このファーストビューに簡潔かつ効果的に表示されています。
トップページ下方も、新着情報や天気情報、ライブカメラ映像などの案内となっており、すべての富士登山者が「今」必要とする情報がトップページだけでほぼすべて確認できるように配慮されています。
4 富士登山オフィシャルサイトの特徴
富士登山オフィシャルサイトは、公式かつ公共性の高いサイトとして、安心感と信頼性を基盤に、「自分に合った登山」「安全な登山」「環境への配慮」を重層的に伝えています。
例えば「弾丸登山は危険です」「ゆとりある登山をしましょう」と、登山者の気持ちに寄り添う語り口が優しい印象を残します。
- 登山ルートの詳細比較:4つのルート(吉田・須走・御殿場・富士宮)の標高、所要時間、距離、傾斜、山小屋の状況などが一覧表で比較されており、選択の参考になります。
- 安全対策への配慮:高山病への注意喚起、山小屋の利用推奨、水・装備の注意事項、緊急時対応まで丁寧に書かれています。
- 運営主体の信頼性:環境省と両県が共同運営しており、法令や自然保護にも配慮した内容。
- 更新性の確保:新着情報やお知らせがトップで見やすく更新され、最新の通行予約や返金対応、体力に不安な方へのチラシ案内などが掲載されています。
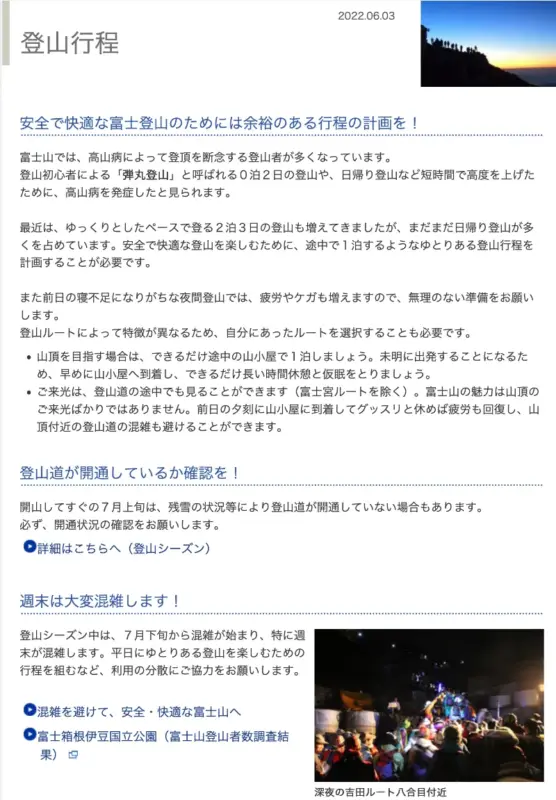
サイトの色彩
背景色:白
メインカラー:瑠璃紺
サブカラー:薄藍(シアン)
アクセント(注意喚起)カラー:赤
官公庁が運営するサイトらしく、落ち着きのある青系統でまとめています。その「青と白」の中では「赤」がより目立つ色となり、注意喚起の効果が高まっている印象です。
ロゴマーク
ヘッダーに表示されるロゴマークは、簡略化された富士山のイラストです。
山頂の下に雲を描く事で山の高さが強調され、伸びて下線となった長い裾野はいかにも富士山らしく、富士登山のオフィシャルサイトに相応しいです。
文字中心の構成
イラストや写真を効果的に使用しているページもあるのですが、文字中心で構成されたページも目立ちます。視覚に訴える工夫がされた記事と、大切な情報を淡々と伝えるページの差が大きく感じるといった印象です。そのため、視覚での直感的な訴えかけにやや弱さを感じました。
視覚情報の少ないページには、タイトルにも画面にリズムをもたらしたり、大きく目を引く工夫は感じられません。PDFリンクでの図表の提供もあるのですが、記事部分には単調な印象を受けてしまいます。少し「お役所的」な面が感じられる部分です。
漢字かなまじりの日本語版は、それでもまだ画面に変化がありますが、外国語版での表示では、単調さがより際立つように感じました。論文か公文書のような印象です。
![]()
5 アプリの紹介
富士登山オフィシャルサイトでは2つのアプリを紹介し、安全な登山のために利用を推進しています。
富士山アプリ:ルート案内
株式会社ヤマレコが運営する、富士山の登山に特化した無料のGPS地図アプリです。
主な対象ユーザー:初めて富士山に登る人。道迷いの不安を軽減したい人。
特徴
- オフライン対応: 登山前に地図をダウンロードしておけば、圏外でも現在地を特定し、道迷いを防ぎます。
- ルートナビ: 吉田、須走、御殿場、富士宮の4つの主要ルートに対応しており、ルートを外れると音声と振動で警告します。
- 情報表示: 山小屋の情報や、他の登山者の記録、現在の富士山の状況などを確認でき、登山計画をサポートします。
- 登山記録: 歩いた軌跡を記録し、オリジナルの「登頂証明」を作成してSNSでシェアすることも可能です。
コンパスEX:登山届・リアルタイム情報確認
「山と自然ネットワーク」が運営する、登山計画の作成と登山届の提出に特化した安全管理ツールです。
主な対象ユーザー:登山計画の段階から安全対策を徹底したい人。オンラインで登山届けの提出をしたい人。
特徴
- 登山計画の作成: 国土地理院の地図を用いて、簡単に登山ルートを計画できます。過去の記録から自分のペースに合った計画を立てることも可能です。
- オンライン登山届: 作成した登山計画書をオンラインで提出でき、万が一の際には警察や関係機関との情報共有をスムーズにします。
- 安全管理機能:登山計画に記載した家族や友人と位置情報や安否を共有できる「フットプリント」や、気象予報・日の出入り時刻の確認機能など、安全登山をサポートする機能が充実しています。
- 多機能性:リアルタイムの天候や落雷情報、登山中のGPSログ記録、登山後の記録編集など、登山の一連の流れで役立つ機能が多数搭載されています。
6 ユーザーインターフェース
富士登山オフィシャルサイトの目的、『安全な富士登山を推進し、富士山の適正な利用を推進する(富士山における適正利用推進協議会」について)』為には、必要な情報を確実にユーザーに届ける必要があります。
サイトのユーザーインターフェースは、誰に、何を伝えるかを明確に設定して設計されている印象です。
ナビゲーション
トップにはクリアなメニューが並び、訪問者は自分の立ち位置(初心者かリピーターか)によってページ移行ができます。
また、アイコンイラストが目立つ大きなボタンリンクが下に並び、更にわかりやすいナビゲーションを実現しています。
多言語対応
世界遺産に登録され、世界中からの登山客、観光客が訪れる富士山ですから、訪日ユーザーへのアナウンスは重要な位置を占めます。
このサイトでは、日本語の他に、English、简体中文、繁體中文、한국어という多言語リンクが明示されており、訪日外国人にも配慮が感じられます。
英語版では記事がインバウンド向けに再編成されているようです。中国語、韓国語のページは内容を絞っていますが、10分を超える動画に字幕が付き、メインの案内役となっています。

SNS連携とアプリの紹介
トップページ下部のスライドバナーにはXへのリンクが設けられています。
また、「登山規制」ページでは、山梨県・静岡県それぞれのページ下部にfacebook・X・LINEへのリンクがあり、様々な経路からリアルタイムの情報共有や発信に注力している事が伝わります。
また、上記項目で述べた2つのアプリも、このサイトの目的の補佐として有効に働くツールとしてリンクが設けられています。
レスポンシブ対応
しっかりとモバイル対応されており、現地での確認が必須の情報提供にきちんと対応しています。
まとめ
「富士登山オフィシャルサイト」は、富士山の管理に関わる、環境省・山梨県・静岡県が協力して運営しているサイトです。富士登山を、観光促進方面ではなく、「いかにして事故を未然に防ぐか」という面に注力しているのが特徴的に感じました。
官公庁がそのような取り組みを行う背景には、日本一高く、登山には一定の覚悟と準備が必要な山が観光地化されて、安易な意識の登山者による遭難が相次いでいる事があるでしょう。
歴史的にも富士登山は日本人の心に深く根付いた願望であり、また、世界遺産として国外からの訪問客の目的地ともなっていることを考えると、危険だからとやみくもに規制するのには限界があるでしょう。正確な情報提供をし、安全な富士登山を促す取り組みとして、このサイトの存在は大きいと考えます。
情報の網羅性、安全性への注意喚起を登山者への共感を誘う丁寧な語りかけで行うこのサイトは、非常に心強い案内所となっています。
また、多言語対応やSNS連携によって幅広い層に届けるという意識も強く感じます。
そして整理された情報の構成は、多くの登山者にとって安心して情報を集められる基盤となっていると感じます。欲を言えば、視覚に訴えるビジュアル中心のデザインになると、より多くの人々の関心を惹き、効果が膨らむのではないかと思います。
とはいえ、何よりトップページに安全情報を集約させていることに大きな意味を感じます。ユーザーの一番必要な情報をまとめて発信するという目的がはっきりと伝わります。
トップページの情報を軸に見てみると、使いやすいUIと官公庁による正確で豊富な情報提供に支えられたこのサイトが、信頼できる案内役であることは間違い無いでしょう。
富士登山者全員が是非このサイトをパートナーにして挑戦して欲しい、そして安全に目標を達成出来ますように、そんなふうに祈念してしまうサイト体験でした。

